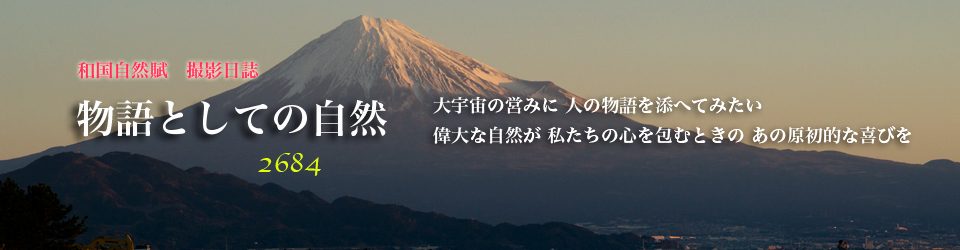その時、私は北海道東部、早春の雪が美しく輝く知床の森の中にいた。
静寂の中に風の音と海鳴りだけがかすかに耳に響く穏やかなこの午後に
東北地方を中心に関東・中部を襲った大きな揺れを感じることはできなかった。
撮影中は情報隔離状態の私が今回の事態を把握したのは、翌朝になってからだった。
*
本州の家族親族の無事が分かって安堵したものの、被害の実態が判明するにつれて暗澹たる気持ちになる。
同情ではない。突然に非日常に投げこまれ、問答無用の現実に命を曝されている被災者の心境をいくらリアルに想像しようとしても出来はしない。
もし私に被災体験があったとしても「今このとき」の彼らの必死の思いを共にできるはずもない。
ただ、大切なものの一切を失ってしまった彼らを待っている堪え難い空虚と絶望を想うとき、この世に生きていく誰もが逃れようのないある種の悲哀が強く胸を締めつける。
*
日常は突然前触れもなく非日常に変貌した。その過酷な現実に思いを馳せるとき今自分がここにあたかも部外者として存在していることの意味を考えざるをえない。
自分が当事者でないことには何の必然性も合理的理由もないからだ。
人間社会とは何と危うい微妙なバランスの上にある存在なのだろうか。
*
札幌に戻ってきたのが13日、こちらは幸い何事もなかったかのように動いている。
歴史上希有なこの自然災害で心ならず鬼籍に入られた方々のご冥福を心からお祈りする。
そして困難な復興に立ち上がるすべての同胞とその心を合わせ支えんことを願う。