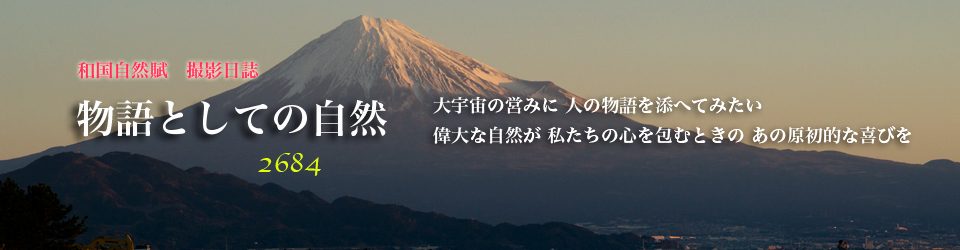知床半島の川で撮影しているとき
たくさんの遡上するカラフトマスを見た。
長い旅の果てに帰ってきた彼らは
故郷の川で 最後の仕事 繁殖の営みを終えて
今 眠りにつこうとしている。
早朝 冷え込んだ秋の川で
ふらふらと、力尽きて流される一匹のカラフトマスを見た。
懸命に体をくねらせて川岸の溜りにたどり着くと
先に逝った仲間の体に寄り添うように静かに横たわる。
瞳に映る晩秋の高い青空に 白い雲がひとすじ流れていた。
ああ
なんだろう この胸の底にうずく哀しみは
魂の共鳴とでもいうような
深いところから湧き上がる哀愁に満ちた感動は・・・
その瞬間
僕はもしかすると
生命の根源のようなもの 宇宙の真理というものに
億万年のときを飛び越えて
触れていたのかもしれない。
知床連山から吹き下ろす秋の風は
かすかに冬の匂いがした。