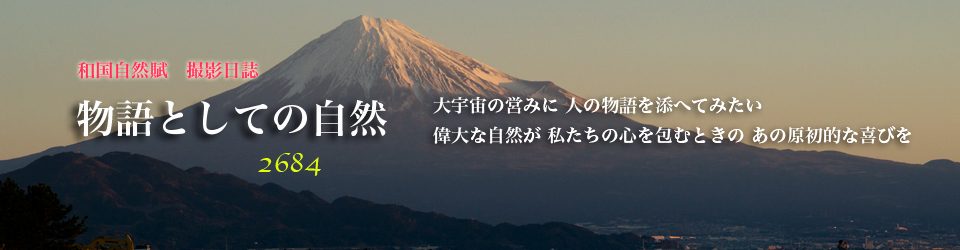ここ北海道でも、ようやく鳥たちの夏冬交替の季節となりました。
冬の海のカモメたち、湖のオオハクチョウ、小さなツグミやベニヒワたちは繁殖のために北へ旅立ちました。
入れ替わりに南からは ノゴマ、アオジ、ノビタキなどが賑やかなさえずりと共にやってきました。
年中変わらずにいるカラスやトビ、シジュウカラやヒヨドリたちも元気に飛び回っています。
- アオジ♂
- ノビタキ♂
私たちにとって渡り鳥の代名詞はなんといっても雁でありましょう。
わが先人たちは雁の渡りを春秋の風物詩として長く愛してきました。
春がすみ たつを見捨ててゆく雁は 花なき里に住みやならへる
伊勢 (古今和歌集 春の部 上)
かへる雁 雲路にまどふ声すなり 霞ふきとけ このめはるかぜ
読み人しらず(後選集 春の部 中)
春霞たちてくもゐになりゆくは 雁のこころのかはるなるべし
読み人しらず(後選集 春の部 中)
「かすみのように咲き匂う桜を待たずに北に去る雁たちは、きっと花の美しさを知らないのでしょう」
「春霞がたって雁が道に迷う声がするよ、風よ吹いて霞みを飛ばしておくれ」
「霞が雲に変っていく、心を決めて名残を捨てて旅立つ雁の悲しい心だろうなあ」
こうした歌には平安朝の人々が抱いた雁(自然というもの)への素朴な愛情が美しく感じられます。
国民性というものは、こうした素朴で自然な風土に対する愛情が自然に育むものなのでしょう。
物質欲に冒された現代に生きる我々には、思い出さねばならない大切なものがあると思います。
***
私も毎年マガンの渡りの中継地である美唄市の宮島沼に出かけます。
陽炎のゆらぐ沼のむこうに、春霞に浮んだ残雪の山々を眺めると心が慰められます。
春の渡りは命が生まれ輝く夏に向かう、悦びと力に溢れているようです。
対照的に秋の渡りは、厳しい冬を迎える慌ただしさと寂しさを感じます。
- 夜明け前の空知平野
- ふきのとう
宮島沼のマガン6万羽、その夜明けのねぐら立ちはものすごい迫力です。
轟音とともに空を埋め尽くして舞い上がった雁が周辺の畑へ散っていきます。
夕方まで採餌した彼らは、日暮れどき、また大きな群れで沼へ還ってきます。
その帰る数が毎日だんだんと減ってゆき、ある日すっかりいなくなるのです。
宮島沼でしっかり気力と体力を養ったかれらが無事に故郷のシベリアへ
辿り着くことを願いながら、私も彼らとの貴重な時間を共有するのです。
- 舞い上がったマガンたち
- 水面を駈けて飛び上がるマガン