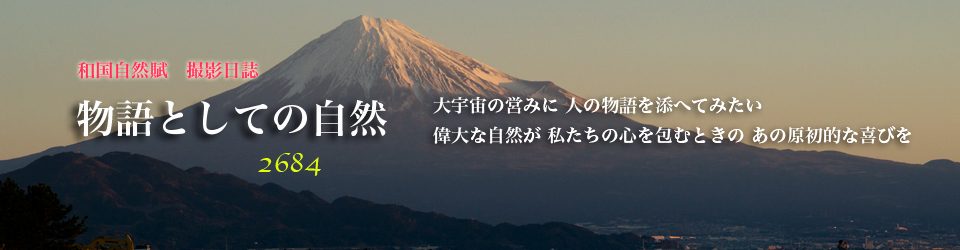◾️平成をふりかえれば
令和の幕開けからひと月が経ったいま、改めて平成の時代を振り返って思うことがある。
大自然災害の頻発や、子供達のいじめや猟奇殺人などが まるで日常茶飯事のようになっていた。
何か我々の根深い場所が ひどく病んでいることを強く感じていたものだ。
巨大な嘘を積み重ねてきた「戦後日本」の矛盾が、その腐敗を隠しきれず噴出してきたのだと。
世の真実を見抜くのは 合理ではなく 直感である。
東日本大震災に際して石原都知事が「天罰」という言葉を用いて批判されたことがあった。
だが石原氏の痛切な思いに 心底共感した日本人は私だけではあるまい。
空虚な言葉を流行らせて 健全な秩序を壊していく リベラリズムが世界中を混乱させてきた。
「自由、平等、人権」などの抽象的で中身のない言葉が 金科玉条のように扱われたために
われわれの言葉は軽薄となり それとともに物事の価値はすべてが相対化し、そして空洞化した。
「何よりも個人の個性が大切だ」と宣伝・神聖化されて、公的な道徳は混乱し そして劣化した。
◾️「イイとこ取り」の考え方ではダメ
「経済だけ考えればイイ」といって、人間の精神生活の面を考えない者
ありもしない「差別」を設定して「弱者を守れ」と叫び「イイひと」を演じる者
心地イイ話だけを聞いて、不都合な真実や面倒な事実は黙殺、無視してやり過ごす者
安易な「イイとこ取り」で一生を過ごそうと考える、戦後日本人の特徴のひとつかもしれない。
この「イイとこ取り」が精神を腐らせた。自己の都合を優先させ 現実を見る目を失わせた。
無知蒙昧を恥じず、 他者を尊敬する習慣も消えて、己を鍛えることを面倒に思うようになった。
そして「あるがままの君、そのままの君がイイんだ」と言われたがる薄弱な人間が増殖した。
だから骨のある若者たちは 理想の人間像、社会像を「昔の日本人」に求めざるを得ない。
古事記や万葉集、神社は静かなブームである。若い女性たちの間では縄文ブームまである。
昔の日本人は泣き言をいわずに謙虚に真剣に生きる強さがあった。戦にも勇敢に立ち向かった。
モノは豊富だが人間が呆けた現代、若者たちは 真面目に強く生きるお手本を欲している。
これは日本の長い歴史の強みだが、そこに頼る以外にないのは 危機的な状況ともいえる。
つまり戦後日本人の姿はもはや 生きるうえで御手本にならないものに堕ちているということ。
この恥ずべき現実を 我々はごまかさずに 真摯に受け止めて考えなくてはならない。
◾️国際主義者との戦いは 終わっていない
「戦後は次の戦争で終わる、次は勝てばいいんです」(経済評論家・渡辺哲也氏)とは面白いが、
じつは戦争は この百年来、形を変えながら 今も絶えず続いているというのが私の認識だ。
欧米の近代を作ったユダヤ思想は 国家を否定し 国境なき市場による世界統一を目指す考え方。
欧州の大財閥ロスチャイルドを後ろ盾に 米国のウォール街が金融力で世界を支配してきた。
その国際主義のユダヤ勢力に対してわが日本の歴史と精神文化を守る熾烈な戦いが続いている。
これこそが あの仏革命から20世紀の世界大戦まで一貫する、世界動乱の構図の核心なのだ。
かつて「大東亜百年戦争」と喝破した林房雄氏の慧眼は、この本質を見事についていたと思う。
わが日本は 世界最古の家系・皇室をいただく国であり、いわば世界の国の模範的存在である。
だからこそ世界を統一したい国際主義者にとり最大かつ最後の敵として、標的にされてきた。
戦後 猖獗を極めた国際主義だが、2年前に米国にトランプ大統領が誕生して情勢は急変している。
「自国ファースト」国民の安全と繁栄を最優先する政策が 堂々と語られるようになってきた。
わが国では政財官すべてが鈍麻して対応できずにいるが、国民の間では 徐々に世界の真実を知ることで 本来の国家観に目覚める動きが見られるのは 将来に向け明るい兆しである。
令和の御代は「歴史ある日本」の伝統を尊び、ご皇室や祖先への敬愛心を新たにしたいものだ。
それが 今を生きる私たち大人が 日本人としてまず考えるべきことであろう。